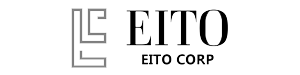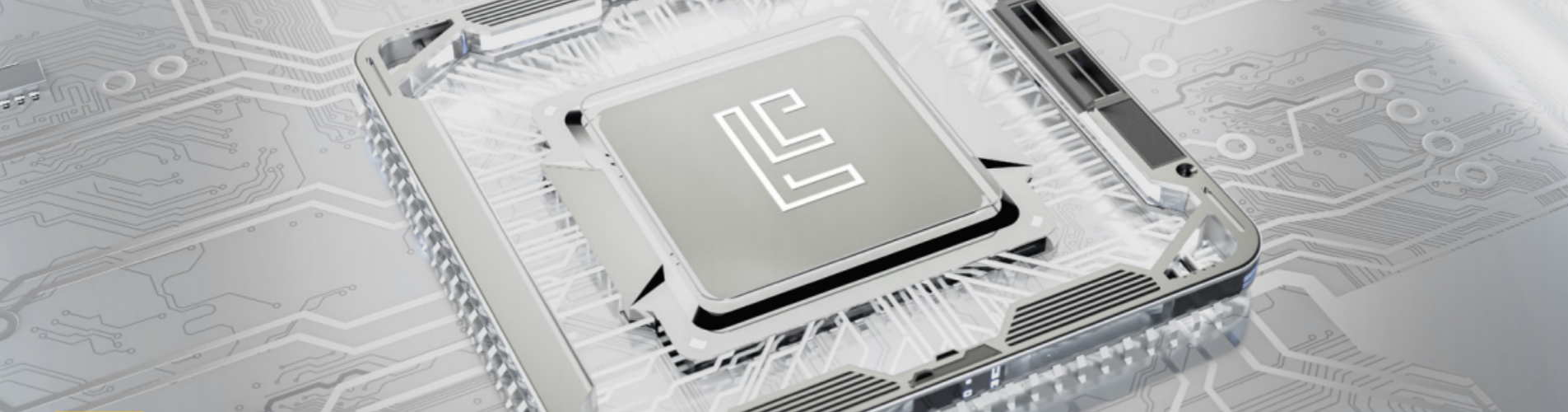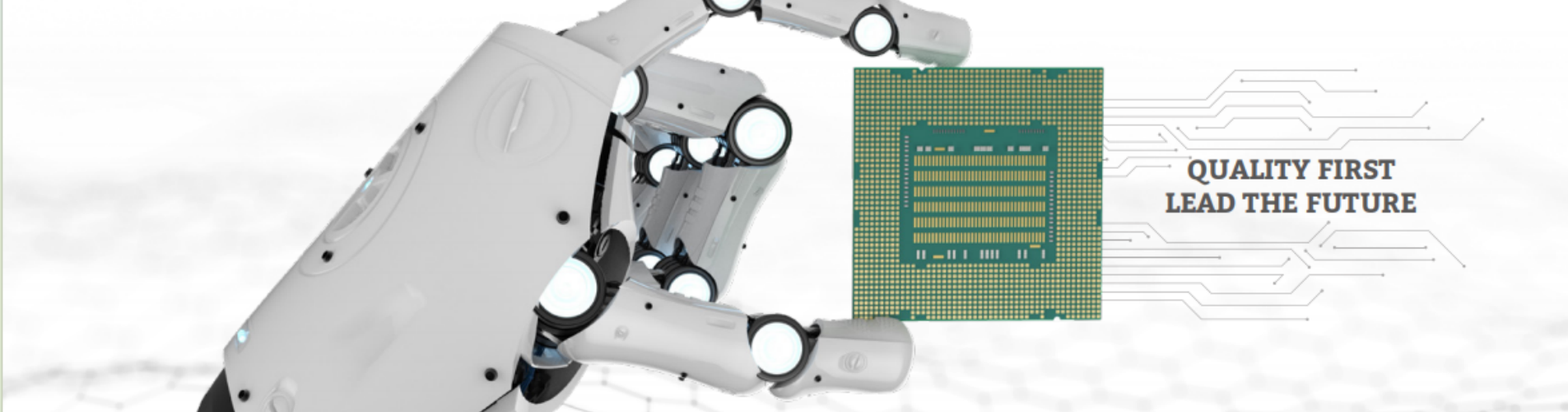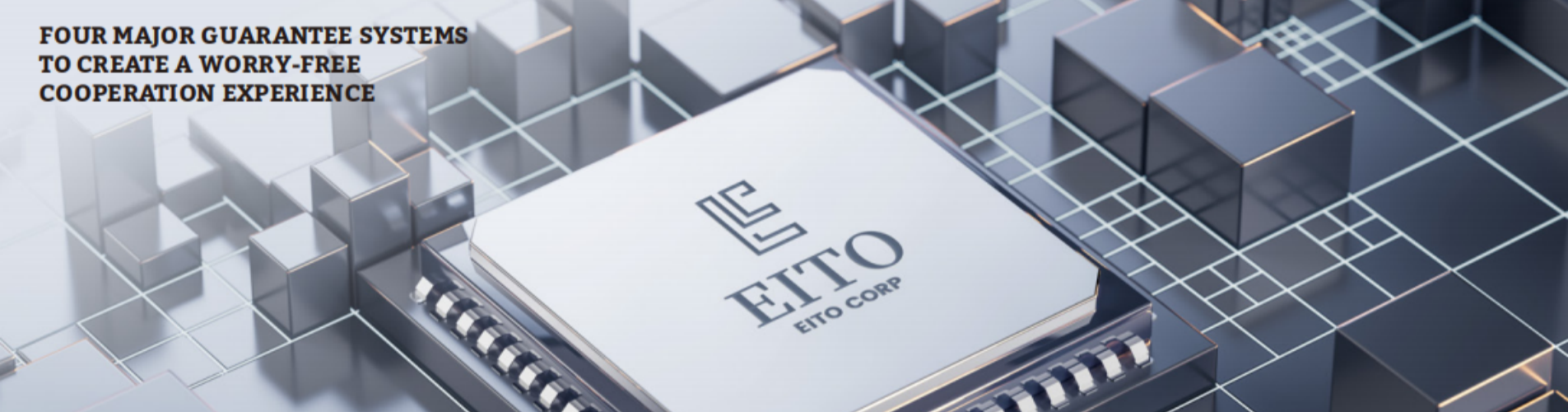電話:81 3-6863-5366
米国の関税圧力下で、インド/ベトナム製造が恩
トランプは関税手段を通じて製造業をアメリカに還流させたいと考えていますが、アメリカが世界全体に対する関税引き上げを宣言したとしても、消費電子製品の産業チェーンクラスターは依然として東アジア、南アジア、東南アジア地域を中心としています。
今年4月、米中両国の関税紛争はエスカレートし、後に双方とも91%の対抗関税を撤廃し、両者の主要関税構造は「10%の基礎関税(2025年7月8日まで)+24%の追加関税(2025年8月11日以降)」に調整されました。また、半導体や電子製品については、一部の品目では技術禁止で追加税率が適用される可能性があり、中国で生産した品目の総合税負担は30%を超える可能性があります。
アップルは2025年5月、生産能力の大部分をインドとベトナムに移すと発表しました。当時、トランプ政権はインドに26%、ベトナムに46%の関税を課すと発表しました。2025年7月、アメリカはベトナムに対する関税を20%に引き下げることを確定しました。
実際の関税は「米国部品20%免除」の原則に影響されます
4月中旬、米国のホワイトハウスのウェブサイトは、22ページの製品免除リストを公開しました。このリストは、「米国の部品20%免除」(コンピュータ、携帯電話、半導体、ディスプレイなどの20の電子製品の輸入を含む)の原則を示しています。米国は製品の「非米国」部分にのみ課税します。この文書は、「組み立てた製品を海外で生産して本国に販売する」というアップルのやり方では、関税面で「米国分」を除く必要がある可能性を示唆しています。
日本経済新聞はこれまで、Fomalhaut Techno Solutionsと協力して、いくつかのiPhoneを分解してきました。このうち、999ドルのiPhone 16 Proのハードウェアコストは約568ドルで、A18 Proチップ(tsmcがファウンドリ、コスト135ドル)とOLEDスクリーン(サムスン電子が供給、コスト110ドル)のコストが最も高いです。ただし,iPhone 16 Proについては,具体的な米国成分比は示されていません。iPhone 15 Pro Max(1,199ドル)の分解調査では、米国が33%、韓国が29%、日本が10%、台湾が9%、中国が2%となっています。
「米国成分20%免除」が最終的に実現すれば、iPhone 15 Pro Maxの米国部品の33%が関税控除を受けることになると試算されています。セット価格1,199ドルで計算すると,約800ドルで,実質的な税負担は約3割減少します。iPhone 16 Pro、iPhone 17シリーズの米国比率がやや低くても、20%のハードルに到達すれば、同様の恩恵を受けることができます。
アメリカはベトナムに20%の関税を課しましたが、インドにはまだ発表されていません
2025年7月初め、ベトナムはアメリカへの輸出品に少なくとも20%の関税を、ベトナムを経由する第三国の貨物には40%の関税を、アメリカからベトナムへの輸出品には関税を免除することでアメリカと合意しました。
記事送稿日までに、米国はインドに新しい関税書簡を発表していません。インドメディアによると、「米国は、米国がインドに課す予定の関税率を20%以下に引き下げる可能性のある暫定的な貿易協定をインドと結ぶために努力しています」。一方、トランプ氏側は、インドに20 ~ 25%の関税が課せられる可能性があると主張しています。インドに対するアメリカの最終税率はまだ決まっておらず、両国は8月1日の関税期限を前に貿易交渉を続けています。
以上の情報を総合すると、米国の関税が正式に実施された後、中国大陸で組み立てられた電子製品が米国に販売される場合、米中二国間関税の影響を受けることになります。加えて、中国の人件費はますます高くなっており、ベトナムやインドは人件費が安いだけでなく、関税の面でも中国より優位にある。
現在、両国は電子産業のクラスターを形成しており、インドで生産するにしてもベトナムで生産するにしても、中国で生産するよりも総合コストが低いのです。これもアップルが米国産の生産能力をこれらの国に移転する重要な理由だと信じています。
まだ多くの国々がアメリカと交渉しています
2025年7月30日時点で、米国は対euで15%、ベトナムで20%、日本で15%、フィリピンで19%……いまでもアメリカ側と関税について話し合っている国はたくさんあります。アメリカが各国に関税を課している背景には、企業が合意した国や税率の低い国への註文や生産能力の移転が加速しています。
これと同時に、まだ米国との交渉が成立していない地域のサプライチェーンは、8月1日に発効する可能性があるより高い税率を回避するために、「友岸」への配置を考慮して、リンクの一部をより低い関税の国に移転する可能性があります。全体的に見て、関税の違いは企業の立地と世界の生産能力の再均衡の考慮要素の一つになっています。